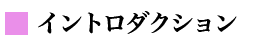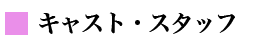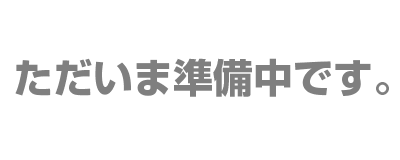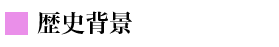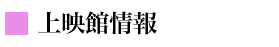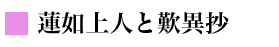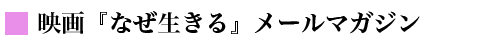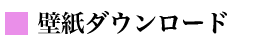(1)親鸞聖人と「浄土真宗」
教科書には、「浄土真宗の開祖は、親鸞聖人」と書かれています。
しかし、親鸞聖人は、「浄土真宗を開いたのは法然上人であり、浄土真宗とは『阿弥陀仏の本願』の別名である」と明言されています。
親鸞聖人には新しい宗派を立てる気持ちは、少しもなかったのです。
どんな人をも本当の幸福に救う「阿弥陀仏の本願」のことを、親鸞聖人は「浄土真宗」と言われていたのです。
しかし、親鸞聖人は、「浄土真宗を開いたのは法然上人であり、浄土真宗とは『阿弥陀仏の本願』の別名である」と明言されています。
親鸞聖人には新しい宗派を立てる気持ちは、少しもなかったのです。
どんな人をも本当の幸福に救う「阿弥陀仏の本願」のことを、親鸞聖人は「浄土真宗」と言われていたのです。
(2)本願寺の設立
京都に「本願寺」を設立されたのは、親鸞聖人の曽孫である覚如上人でした。
親鸞聖人がお亡くなりになったあと、「阿弥陀仏の本願」を、誤解、曲解して伝える人が多く現れました。
その現状を嘆き、親鸞聖人の教えを、正しく伝えるために、覚如上人が「浄土真宗」という名で、新たな教団を設立されました。活動の拠点として、京都の親鸞聖人の墓所に建立された寺院が「本願寺」なのです。
寺院といっても、本堂が三間(約6メートル)四方の、小さな建物でしかありませんでした。
親鸞聖人がお亡くなりになったあと、「阿弥陀仏の本願」を、誤解、曲解して伝える人が多く現れました。
その現状を嘆き、親鸞聖人の教えを、正しく伝えるために、覚如上人が「浄土真宗」という名で、新たな教団を設立されました。活動の拠点として、京都の親鸞聖人の墓所に建立された寺院が「本願寺」なのです。
寺院といっても、本堂が三間(約6メートル)四方の、小さな建物でしかありませんでした。
(3)蓮如上人の登場
本願寺のトップを、当時は「法主」といいました。
覚如上人は自らを3代目と定め、初代が親鸞聖人、2代目が親鸞聖人の孫の如信上人とされました。
あくまで親鸞聖人の教えを、正確に、より多くの人に伝えるために、このような組織を作られたのです。
そして、この映画の主人公・蓮如上人は、8代目の法主として歴史に登場されます。
「法主」と聞くと、偉い坊さんで、雲の上の人のように感じるかもしれません。しかし、蓮如上人は、民衆の中に飛び込んで、共に笑い、共に泣き、共に語り合われた方です。その人柄を表すエピソードの一つとして、この映画には、蓮如上人が、赤ん坊のおしめを洗われているシーンを入れました。
「そんなことまで、されるはずがない」と思われるかもしれませんが、蓮如上人の言行録として有名な『御一代記聞書』に記されています。
覚如上人は自らを3代目と定め、初代が親鸞聖人、2代目が親鸞聖人の孫の如信上人とされました。
あくまで親鸞聖人の教えを、正確に、より多くの人に伝えるために、このような組織を作られたのです。
そして、この映画の主人公・蓮如上人は、8代目の法主として歴史に登場されます。
「法主」と聞くと、偉い坊さんで、雲の上の人のように感じるかもしれません。しかし、蓮如上人は、民衆の中に飛び込んで、共に笑い、共に泣き、共に語り合われた方です。その人柄を表すエピソードの一つとして、この映画には、蓮如上人が、赤ん坊のおしめを洗われているシーンを入れました。
「そんなことまで、されるはずがない」と思われるかもしれませんが、蓮如上人の言行録として有名な『御一代記聞書』に記されています。

(4)本願寺の爆発的な発展
蓮如上人が法主に就任される前の本願寺は、実に、さびさびとした状態でした。本願寺へ来た門徒が失望のあまり、帰り道には別の寺の門徒になった例もあるほどです。
しかし、蓮如上人が43歳で、本願寺8代法主に就任されるや、様相が一変します。
蓮如上人の法話を聞きに来る人が、急速に増え、本堂に入り切れなくなったのです。そのため、本堂の増築工事が、繰り返し行われました。
ここで、寺の本堂の目的を確認しておきたいと思います。
普通の仏教の寺院では、本堂を使う時は、葬式、法事とか、年に何回かのイベントや儀式で読経する時ぐらいでしょう。
浄土真宗の場合は、本堂を使う目的が、全く違います。本堂は、法話を聞く場所なのです。しかも、多くの人が参詣し、前方から正座して座り、姿勢を正して真剣に法話を聞く場所なのです。
法話は、朝、昼、夜と、続くこともあり、何日も続くことが多くあります。
(真宗王国といわれる北陸では、昭和の中頃まで、365日、いつでも法話が行われている寺が、いくつもありました)
蓮如上人は、京都の本願寺で、ご自身の体力が続く限り、法話に立たれていたことは、いくつもの文献から明らかです。
本願寺には、「もっと聞かせていただきたい」という人が、繰り返し参詣するようになりました。
仏法は、「これだけ聞いたから分かった」という知識欲で聞くのではありません。「なぜ生きる」という、自身の大問題について、聞かせていただきますので、繰り返し聞かずにおれなくなるものなのです。
では、蓮如上人が、どんな話をされたから、それほど多くの人が集ったのか。そこを再現するのが、今回の映画の最も重要なポイントでした。
里見浩太朗さん演ずる蓮如上人の法話を、ぜひ映画で、お聞きください。
しかし、蓮如上人が43歳で、本願寺8代法主に就任されるや、様相が一変します。
蓮如上人の法話を聞きに来る人が、急速に増え、本堂に入り切れなくなったのです。そのため、本堂の増築工事が、繰り返し行われました。
ここで、寺の本堂の目的を確認しておきたいと思います。
普通の仏教の寺院では、本堂を使う時は、葬式、法事とか、年に何回かのイベントや儀式で読経する時ぐらいでしょう。
浄土真宗の場合は、本堂を使う目的が、全く違います。本堂は、法話を聞く場所なのです。しかも、多くの人が参詣し、前方から正座して座り、姿勢を正して真剣に法話を聞く場所なのです。
法話は、朝、昼、夜と、続くこともあり、何日も続くことが多くあります。
(真宗王国といわれる北陸では、昭和の中頃まで、365日、いつでも法話が行われている寺が、いくつもありました)
蓮如上人は、京都の本願寺で、ご自身の体力が続く限り、法話に立たれていたことは、いくつもの文献から明らかです。
本願寺には、「もっと聞かせていただきたい」という人が、繰り返し参詣するようになりました。
仏法は、「これだけ聞いたから分かった」という知識欲で聞くのではありません。「なぜ生きる」という、自身の大問題について、聞かせていただきますので、繰り返し聞かずにおれなくなるものなのです。
では、蓮如上人が、どんな話をされたから、それほど多くの人が集ったのか。そこを再現するのが、今回の映画の最も重要なポイントでした。
里見浩太朗さん演ずる蓮如上人の法話を、ぜひ映画で、お聞きください。

(5)沸き起こる非難攻撃
当時、日本の仏教界で、強大な勢力を持っていたのが、最澄が開いた天台宗延暦寺でした。天皇や朝廷、幕府をも恐れさせる強大な力を持っています。その拠点は、京都の北東にそびえる比叡山でした。
寛正6年(1465)1月10日。比叡山延暦寺の僧兵が、大挙して京都の本願寺を襲撃しました。蓮如上人の命を狙い、建物を全て破壊して去って行きました。
この歴史上の事実は、何を表しているのでしょうか。
象のような巨大な宗教団体・比叡山延暦寺が、なぜ、アリのように小さな本願寺を、襲撃したのでしょうか。なぜ、蓮如上人の命を、執拗に狙ったのでしょうか。
比叡山の檀家が、次々に離脱して、蓮如上人の法話を聞きに行くようになりました。これまで比叡山へ寄付をしていた商人が、本願寺門徒になったため、収入が減ってしまいました。権力者の中にも、本願寺へ参詣する者が出てきました。
比叡山は、「このままでは、日本中が浄土真宗になってしまうのではないか」と危機感を抱いたのです。
巨大な伝統教団が、それほど強烈な恐れを抱くほど、蓮如上人の本願寺は、急速に発展したのでした。
寛正6年(1465)1月10日。比叡山延暦寺の僧兵が、大挙して京都の本願寺を襲撃しました。蓮如上人の命を狙い、建物を全て破壊して去って行きました。
この歴史上の事実は、何を表しているのでしょうか。
象のような巨大な宗教団体・比叡山延暦寺が、なぜ、アリのように小さな本願寺を、襲撃したのでしょうか。なぜ、蓮如上人の命を、執拗に狙ったのでしょうか。
比叡山の檀家が、次々に離脱して、蓮如上人の法話を聞きに行くようになりました。これまで比叡山へ寄付をしていた商人が、本願寺門徒になったため、収入が減ってしまいました。権力者の中にも、本願寺へ参詣する者が出てきました。
比叡山は、「このままでは、日本中が浄土真宗になってしまうのではないか」と危機感を抱いたのです。
巨大な伝統教団が、それほど強烈な恐れを抱くほど、蓮如上人の本願寺は、急速に発展したのでした。

(6)北陸へ、吉崎へ
比叡山の僧兵の暴虐ぶりは、この映画の冒頭から、印象深く描かれています。
蓮如上人は、それでも、「法話を聞きたい」という人があれば、どこへでも赴いて説法されました。しかし、人が集まると、すぐに僧兵が見つけて襲ってきます。
文明3年(1471)の初夏、蓮如上人は、北陸へ向かう決意をされました。
危険の多い近畿地方で法話を続けるよりも、参詣者が、静かに、安心して仏法を聞くことができる場所へ、拠点を移されたのです。
聞法のための本堂建立に適切な場所として選ばれたのが、現在の福井県と石川県の境に位置する「吉崎」でした。
吉崎山という小高い台地が、湖に突き出ています。
この山上に、大寺院が建立され、「吉崎御坊」と呼ばれるようになりました。
蓮如上人は、それでも、「法話を聞きたい」という人があれば、どこへでも赴いて説法されました。しかし、人が集まると、すぐに僧兵が見つけて襲ってきます。
文明3年(1471)の初夏、蓮如上人は、北陸へ向かう決意をされました。
危険の多い近畿地方で法話を続けるよりも、参詣者が、静かに、安心して仏法を聞くことができる場所へ、拠点を移されたのです。
聞法のための本堂建立に適切な場所として選ばれたのが、現在の福井県と石川県の境に位置する「吉崎」でした。
吉崎山という小高い台地が、湖に突き出ています。
この山上に、大寺院が建立され、「吉崎御坊」と呼ばれるようになりました。

(7)吉崎御坊の繁栄
水面に投じた波紋が広がるがように、越前・加賀・能登・越中の北陸地方はいうまでもなく、越後(新潟)、信濃(長野)、出羽・奥州(東北)からも、「安心して法話を聞ける本堂が完成した」と伝え聞き、日ごとに参詣者が増えていきました。
参詣者が増えるにしたがって、「多屋」と呼ばれる宿泊施設が建てられていきました。遠方から訪れた人たちは、何日間も滞在して、蓮如上人の法話を聞いていきます。
わずか数年のうちに、吉崎御坊周辺に、200近い多屋ができたといいます。
蓮如上人は、次のように書き残されています。
「あら不思議や、一都に今はなりにけり。そもこれは、人間のわざともおぼえざりけり。ひたすら仏法不思議の威力なりしゆえなり」
人気のない土地に、数年で200軒もの旅館が建ったようなものです。蓮如上人自身が、「なんと不思議なことか。まさに、阿弥陀仏の偉大なお力の賜物だ」と感嘆しておられるのです。
参詣者が増えるにしたがって、「多屋」と呼ばれる宿泊施設が建てられていきました。遠方から訪れた人たちは、何日間も滞在して、蓮如上人の法話を聞いていきます。
わずか数年のうちに、吉崎御坊周辺に、200近い多屋ができたといいます。
蓮如上人は、次のように書き残されています。
「あら不思議や、一都に今はなりにけり。そもこれは、人間のわざともおぼえざりけり。ひたすら仏法不思議の威力なりしゆえなり」
人気のない土地に、数年で200軒もの旅館が建ったようなものです。蓮如上人自身が、「なんと不思議なことか。まさに、阿弥陀仏の偉大なお力の賜物だ」と感嘆しておられるのです。

吉崎御坊跡地
(8)吉崎炎上
吉崎御坊が繁栄すると、またもや、他宗、他派からの、妬み、そねみが激しくなりました。
時代は乱世です。京の都は、戦のちまたと化し、越前・加賀も、戦乱の圏外ではありません。何が起きても、おかしくない世相でした。
不穏な空気が漂う中、ついに大事件が起きました。
文明6年(1474)3月28日、風の強い夜でした。吉崎御坊の南大門あたりから、突然、火の手があがったのです。不審火であり、放火だといわれています。大本堂は、たちまち猛火に包まれました。
この大火災の中で、蓮如上人に何が起きたのか。
弟子の本光房了顕は、どういう決断をしたのか。
この映画のクライマックスです。
本光房了顕が、非常事態の中でとった行動は、吉崎御坊が炎上してから500年以上たった今日まで、寺の法話、講談、浪曲など、さまざまな形で語り継がれ、大衆に感動を与え続けてきました。
長い間、多くの人々に親しまれてきたドラマが、今回、初めて劇場用アニメーション映画として、あらゆる世代が、涙せずにおれない感動作に仕上がったのです。ぜひ、ごらんください。
時代は乱世です。京の都は、戦のちまたと化し、越前・加賀も、戦乱の圏外ではありません。何が起きても、おかしくない世相でした。
不穏な空気が漂う中、ついに大事件が起きました。
文明6年(1474)3月28日、風の強い夜でした。吉崎御坊の南大門あたりから、突然、火の手があがったのです。不審火であり、放火だといわれています。大本堂は、たちまち猛火に包まれました。
この大火災の中で、蓮如上人に何が起きたのか。
弟子の本光房了顕は、どういう決断をしたのか。
この映画のクライマックスです。
本光房了顕が、非常事態の中でとった行動は、吉崎御坊が炎上してから500年以上たった今日まで、寺の法話、講談、浪曲など、さまざまな形で語り継がれ、大衆に感動を与え続けてきました。
長い間、多くの人々に親しまれてきたドラマが、今回、初めて劇場用アニメーション映画として、あらゆる世代が、涙せずにおれない感動作に仕上がったのです。ぜひ、ごらんください。